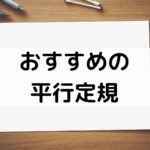一級建築士の製図試験対策で、エスキスは『何を、どのように書けばいいんだろう』と悩んでいませんか?
実は、この記事で紹介する『エスキスの手順』を実践すると、誰でも簡単に素早くエスキスを書けます。
なぜなら、僕も実際に実践して、エスキスができるようになったからです。
この記事では、エスキスの流れをご紹介します。
記事を読み終えると、今後エスキスの手順で何から始めれば良いのか、何を検討すれば良いのか悩むことは一切なく、素早く確実にエスキスができます。
エスキスとは

そもそもエスキスとはどんな意味か、わからない方もいると思うので説明します。
エスキスとは、設計における下書きやスケッチのことを言います。スケッチのフランス語バージョンがエスキスです。
実際のエスキスは、設計のコンセプトや概要を決めて、そのプランを何度も修正することを指すことが多いです。
学校で言うエスキスは、先生やTAに意見をもらいながら修正していく作業を指します。これについては、また別の機会で紹介します。
エスキスの手順
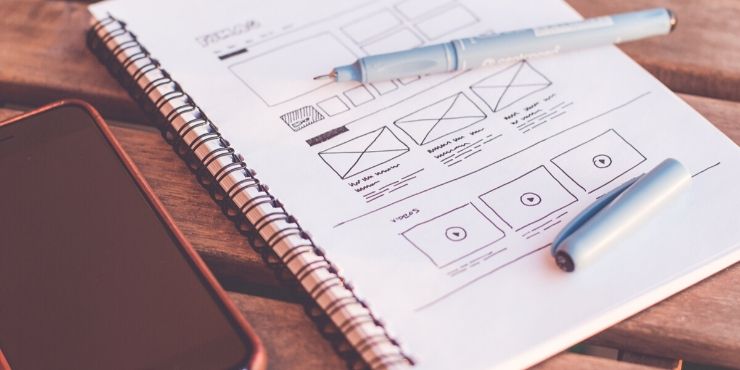
一級建築士の製図試験で必要となるエスキスの手順は以下のようになります。
- 問題文を読む
- 敷地を書く【1/400がおすすめ】
- 敷地に建てられる限界を確認
- 構造と階数確認
- 設備機械室必要の有無チェック
- 断面を確認【コアや吹き抜け】
- 敷地外からのアプローチを考える
- 建物のフレームを考える
- 各階にどの居室をいれるか考える
- ワンスパンを4マスで表現してプランニング
- 面積を算出してチェック
順番にそれぞれの項目について確認してみましょう。
1.問題文を読む
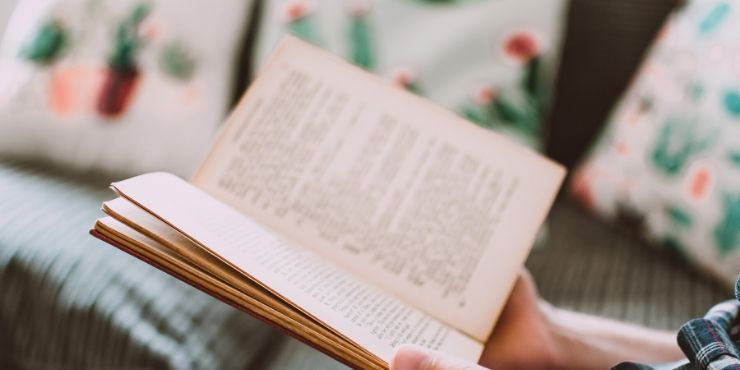
問題文には様々なことが書かれています。大事なポイントを漏らすことなく、しっかり条件を把握しましょう。
特に計画の要となる敷地や周辺の条件、その他の施設、計画の留意事項、採点のポイントである要求図面は確実にチェックしましょう。
全部読み込んでも、もちろん大丈夫です。全部で3回程度は問題文を読み直さないといけなくなるので、好きなタイミングで読み込めば良いと思います。
2.敷地を書く【1/400がおすすめ】

敷地を書いて、その他の施設に必要な範囲を確認します。
駐車場や駐輪場、広場などの面積をチェックして、外構図の案をここで作成します。
おおまかな配置がわかれば十分なので、ここに木を植えるとか、そういう細かいところは最後に考えれば良いです。
ここで大事なポイントは、必ず配置しなければいけない施設を確実に押さえることです。
駐車場や駐車場、広場などをチェックして、外構図の案を作りましょう。
3.敷地に建てられる限界を確認

ここで敷地内に建てられる建物の限界を確認します。
外構図が無いと、どこまで建てられるか明確にできないので、確実に作成しておきましょう。
限界位置を把握することで、建物のボリュームをチェックすることができ、延床面積が条件におさまっているのか確認することができます。
延床面積がどうも足りなくなりそうだという場合は、敷地の建築面積の設定が間違っています。敷地の条件を再度見直しましょう。
4.構造と階数確認

次に階数を確認して、柱のスパンと構造を決定します。
RC造なら6~8mスパン、鉄骨造なら7~9mスパンで想定します。
建築面積と、問題文の延床面積、そして階数と構造から、柱のスパン割を想定して3案ほど作成しておきます。
柱のスパンを確定するのは、室内のプランが確定してからなので、ある程度の自由度を残しておきましょう。
5.設備機械室必要の有無チェック

設備機械室はどれだけ必要か確認します。
外部に設けることができるのはどの緒室か、内部に設ける場合は何階にどれだけの面積が必要かを整理しておきます。
電気室、発電機室、ポンプ・受水槽室、空調機械室などが用途に応じて必要になります。
この項目は、試験前に整理しておけるので、問題文を読んで齟齬がないか確認をしておきましょう。
6.断面を確認【コアや吹き抜け】

断面を確認というのは、高さ方向での制約条件がどれだけあるかを確認するということです。
階段やエレベーターは何個ずつどの辺りに配置しなければいけないのか、避難経路と利用者の通路、管理者の通路を押さえて検討しましょう。
吹き抜けが必要な場合や、体育館のような高さが必要な緒室がある場合も、部屋の配置に大きく制限がかかるので、しっかりと確認しておきましょう。
7.敷地外からのアプローチを考える

計画の肝の1つである、外部からのアプローチについて考えます。
可能なアプローチはどんなものが考えられるか、全種類洗い出しておきます。
これは慣れると特に考えなくても、無意識でできるようになります。
利用者はどこから入るのか、車はどこから入るのか、施設の管理者はどこから入るのか、しっかりと検討しておきましょう。
8.建物のフレームを考える
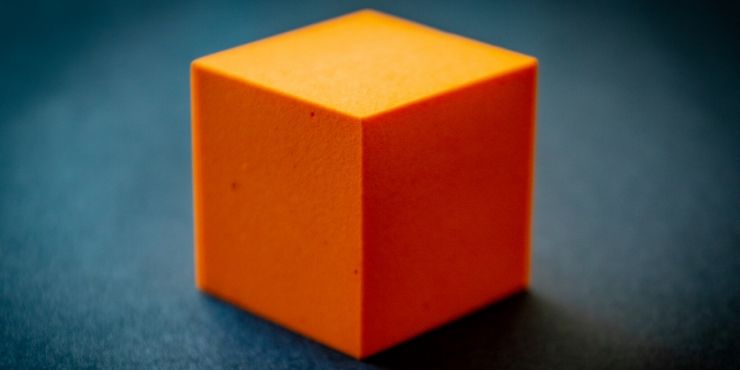
ここまで来たら、建物の外周ラインを設定します。
建物への外部からのアプローチがある程度限定されているので、外構図案と照らし合わせて建物の形状を決めましょう。
構造的に無理のない、現実的な形状にしましょう。
いびつな形状になると、コストパフォーマンスが悪くなるので、可能な限りシンプルにすると良いでしょう。
9.各階にどの居室をいれるか考える

ここでようやく、どの階にどの部屋を割り振るか決めます。
ここで行う割り振りは、用途や部門毎に分けられれば良いでしょう。
1つの用途で複数階にまたがるのは、利便性が悪いです。
電気屋さんなども、この階はスマホの売り場、この階はパソコンの売り場というように、階数で商品がキレイに分かれているので、とてもわかりやすいですよね?
各階の面積の都合でどうしても入りきらないという場合と、そもそも用途が1つしかない場合以外は、原則用途で部屋を階数ごとに割り振りましょう。
10.ワンスパンを4マスで表現してプランニング

ここまでの検討を行って、初めてプランニングになります。
間取りを決める重要な項目です。各部屋の関連性や、日照、通風条件などあらゆる項目を想定しながら、配置を検討します。
配置を検討する時のポイントは、大きな部屋から配置すること、廊下をできるだけまっすぐにすることです。
大きな部屋から配置する理由は、小さな部屋から配置すると大きな部屋が入らなくなるからです。
こういう意見を言うと、小さな部屋から配置してもちゃんと配置できるという意見が出てくると思います。
確かに、小さな部屋から配置しても、ちゃんと配置できる場合もあると思います。
しかし、大きな部屋から配置したほうが、難易度は低くなります。
また、大きな部屋は利用人数も多く、良い条件の場所を確保することでより多くの人の満足度を高めることができるからです。
ですので、プランニングの際は、大きな部屋から配置しましょう。
次にコアや吹き抜けの位置を検討します。
各階に影響が大きいので、全ての階のバランスを見ながら配置しましょう。最後に小さな緒室を配置します。
廊下がまっすぐになるように、適宜広さを調整しながら配置していきます。
部屋が必要以上に大きく、または小さくなりすぎないように注意しましょう。
10%以上面積に差があるときは、適切とは言いがたいです。柱のスパン割と各室のバランスを考えて配置しましょう。
11.面積を算出してチェック

プランニングができたら、延床面積を算出して指定の面積におさまっているか確認します。
おさまっていなければ共用部の面積が多すぎるので、廊下を狭くしたり、設備機械室を屋上に配置したりして面積を調整します。
トイレなど、問題文には記載がないが確実に必要な部屋も抜けていないかチェックしましょう。
エスキスの手順が良くわからなかった方はこの本がおすすめです。エスキスの基本的な手順が書いてあります。独学初学者におすすめですが、おさらいをしたい人にもありです。
まとめ
この記事では、一級建築士の製図試験対策で、エスキスは『何を、どのように書けばいいんだろう』と悩んでいる方に向けて、エスキスの流れをご紹介しました。
エスキスを確実に行うためには、流れを把握することが必要です。
それぞれの項目をしっかりと検討してエスキスを行い、一級建築士の製図試験を突破しましょう。